東洋医学
気ってなに??

今回は東洋医学の基本を少しお話ししていこうと思います♪
皆さまからよく聞かれる「気って何ですか?」についてかなり噛み砕いて書かせていただいております。
東洋医学の復習も兼ねて、書いていけたらと思います( ̄^ ̄)!
今回の目標
『気』が何かを説明できるようになる。
「気」がつく単語
早速ですが、「気」という文字がつく単語を思い浮かべてみてください。
「元気」「短気」「空気」「気力」「気合い」「気持ち」「色気」「損気」……
たくさん出て来ますね!
そして皆さんの思い浮かべた単語、それはどれも目に見えないですよね?
目に見えないけど、人の心や体の状態を表す単語が多い。
気を使ったり、気が合ったり、気になったり。
こんな言葉たちから分かるように、私たちは気づかないだけで「気」を身近に感じながら生活しているんです。
そして
この「気」をきちんと理論化しようとしたものが『東洋医学』と言われています。
東洋医学でいう気って?

何となく、気は実態が掴めないけど「ある」ものだという感覚を持ってくださいましたでしょうか?
実は東洋医学でも同じで、気は「目に見えないもの」として捉えられています。
その目に見えないものを「生命活動を支えるエネルギー源」として体系的に捉えました。
気を分類して、規則性を持たせて、理解を深めようとしていったんですね。
それにより、人体の仕組みを気の分類で説明したり、体の不調を気の乱れで説明したりしようとしました。
これが東洋医学の基本要素になる「気」です。
気にも種類がある
気が生命活動のエネルギー源とお伝えしましたが、人体の気はざっくり4つの要素に分けられます。
①元気(げんき)
分布:全身
役割:全ての組織を機能させる最も基本的な気。
情報:親から受け継ぐ『先天の精』が元となり食べ物などから得る『後天の精』で補充
②宗気(そうき)
分布:心(しん)と肺。胸中ともいう
役割:呼吸と血の運行を押し進める。心肺機能
情報:呼吸で吸い込んだ清気(せいき)と飲食物から作られる水穀(すいこく)の精微から生成
③営気(えいき)
分布:血管内
役割:血と共に各組織に栄養を運ぶ
情報:栄養分が多い気
④衛気(えき)
分布:体内から皮膚など全身に分布
役割:外の邪気の侵入を防ぎ、体内に入った邪気と戦って外に追い出す。汗腺の開閉。
情報:気の中で最も動きが早くて活発
ちなみに「元気」は、おへその下の丹田(たんでん)に集まると言われます。へそ下の緩みは気の緩み…と考えてみるのも面白いですね。
気にもはたらきがある
気の分類を見ていただいた次は、気のはたらき(作用)を見ていこうと思います!
体を正常に動かすために欠かせない作用です。

①推動(すいどう)
全身の臓器や組織など、あらゆるものは気に押し動かされて活動している。消化・排泄・発育など。
②温煦(おんく)
体温を一定に保つ。
③固摂(こせつ)
血を漏れ出さなないようにする。
尿や汗や唾液が出過ぎないようにする。
④気化(きか)
❶物質を転換。個体⇄液体⇄気体
❷余分な水分を排泄する。
⑤防御(ぼうぎょ)
体の表面を守り、体内に入った邪気を追い出す。
気は無くならないの??
結論から言うと、生きている限り無くなりません!
ただ、気が不足したり、滞ったり、逆行することはあります。
「あれ、君、今日元気ないね」
そう言われた時、おそらくあなたの「気」は不足しています。
気が不足していることを「気虚(ききょ)」といいます。
逆に、気が充実していると活力に満ちて免疫力も高まっていていわゆる「元気」な状態になります!
「なんか今日、気虚ってるわ〜」
気虚を習った日から、元気がない時は友人とこんなふうにふざけて会話していたことを思い出します笑
気って、なに??
ここまで読んでくださりありがとうございます。
今回は東洋医学の基本の気をお届けしました☆
最後に。
気とは何か、何となくご理解いただけましたでしょうか?
「目には見えないけどあるもの」
「気の作用で生命活動が維持されている」
等々。
人体を理解しようとする点では西洋医学と同じように大切な視点だと感じています。
「気」を説明しようとした東洋医学は、奥が深いですね。
次回は気とセットで重要な『血・津液』のお話しをしていきます🗣️

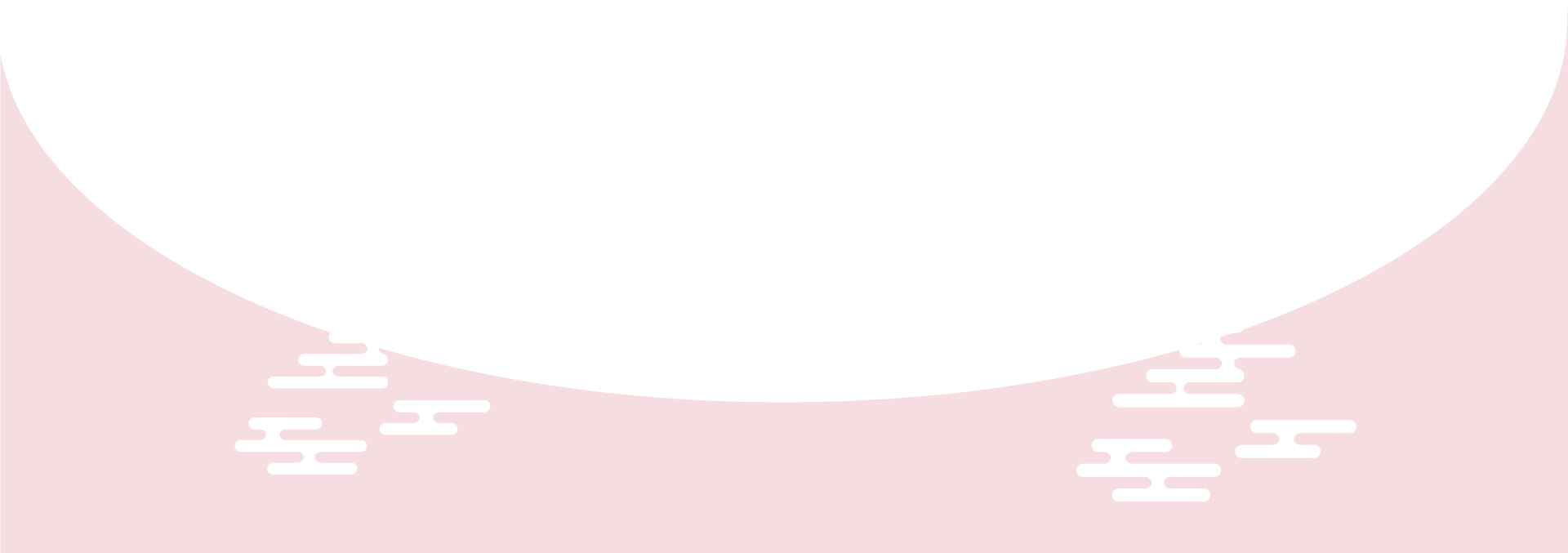
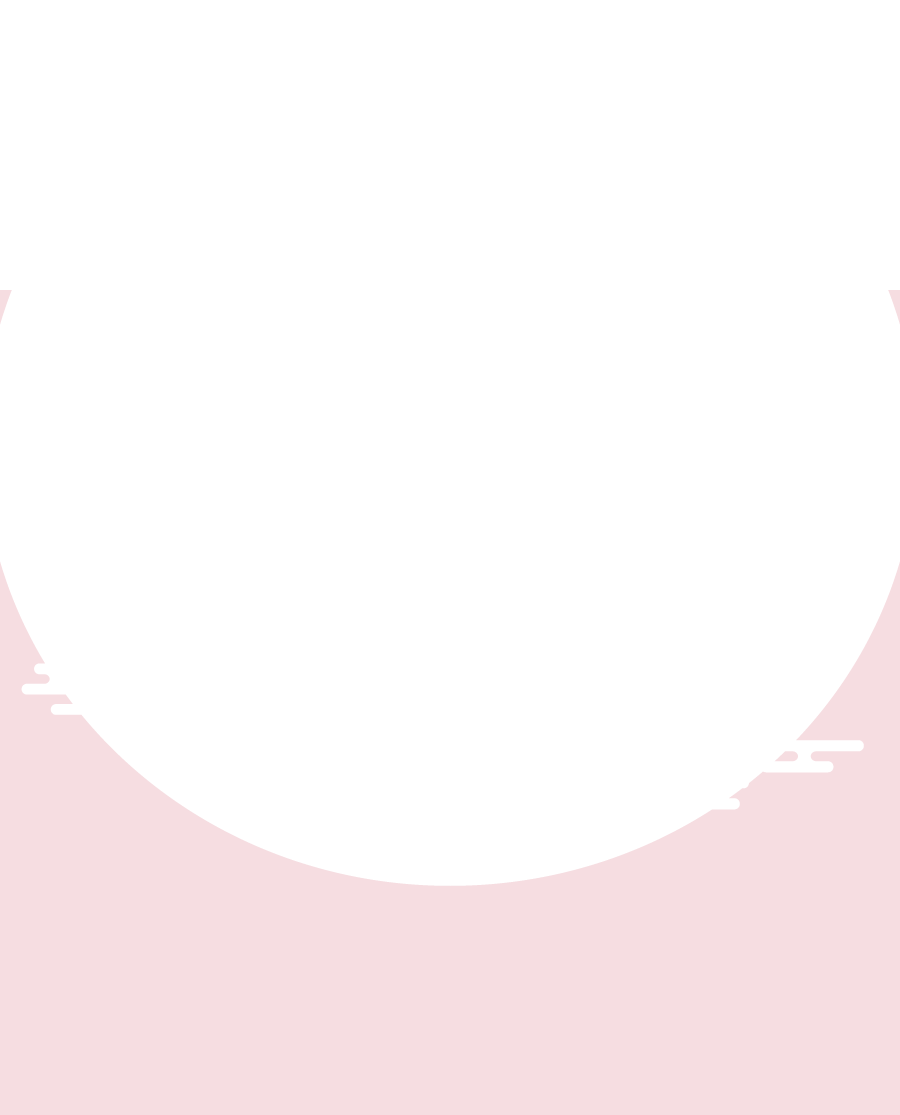
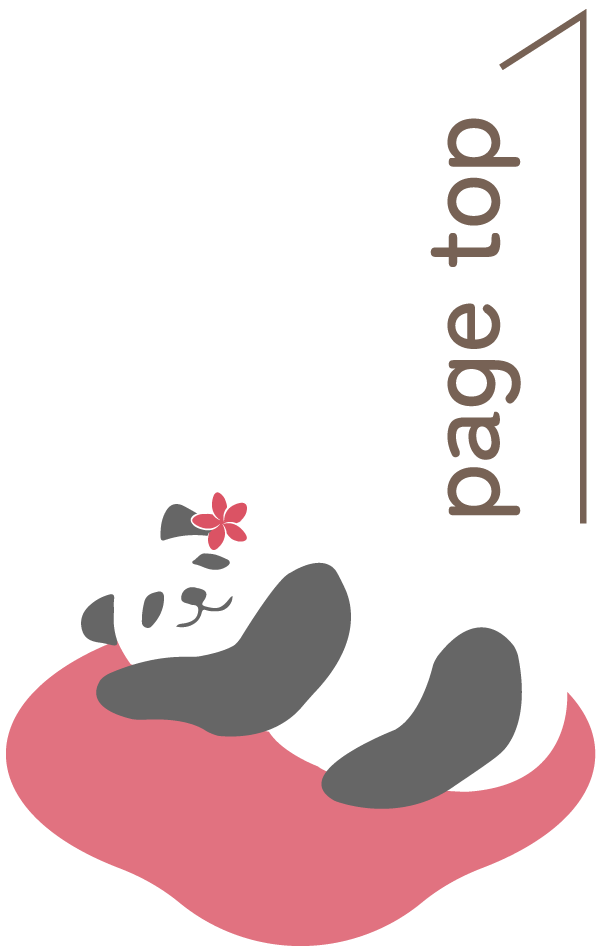
 電 話
電 話 LINE予約
LINE予約